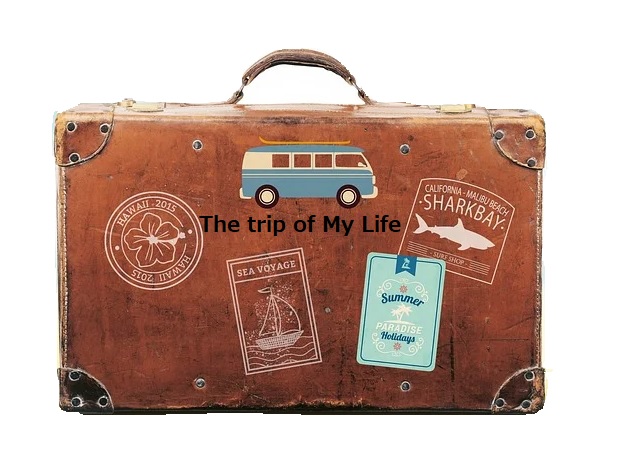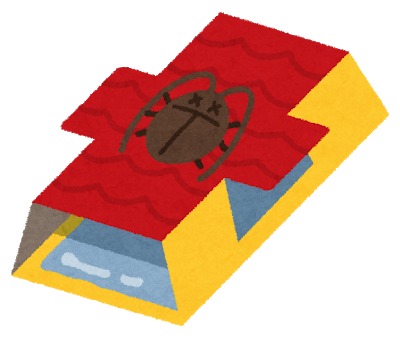今でも強く印象に残っている特別ドラマがあります。それは、太平洋戦争の終戦記念として放映されたタイムスリップ系のドラマ「終わりに見た街」というものです。
太平洋戦争の終結から60年が経過した2005年に終戦記念ドラマとして製作・放映された「終わりに見た街」は、今でも強く印象に残っている物語なのです。
今回は、この物語をもう一度思い出してここへ記しておきたいと思います。
この物語は山田太一原作の小説で、1982年にもドラマ化し放映され舞台上演も行われていたようですが、私が知ったのは2005年の中井貴一と柳沢慎吾出演で再制作されたものでした。
特にこの二人の共演は同じ山田太一作品「ふぞろいの林檎たち」というドラマの時から良く観ていましたし、中井貴一と時任三郎共演の倉本聰脚本「ライスカレー」も感動ドラマの1つとして、年月が経った今でも強く印象に残っています。

この物語は、平凡に暮らしている普通の家族が太平洋戦争の時代へ突然タイムスリップしてしまうものなのですが最後の光景がショッキングであり、人類に対して深い何かを訴えているものでした。
主演の中井貴一や妻役の木村多江、友人役の柳沢慎吾や将校役の柳葉敏郎などの有名俳優が揃っており、このシナリオを見事に演じていました。
戦争時代を経験していない年代にとって、現代には普通にある様々な便利な物が全く無い生活がどれほど不便であるか、食べ物の少ない毎日の生活がどんなに厳しいかを知らされるものであります。
なぜこの家庭だけが突然にタイムスリップしてしまったのか、それは最後まで明らかになることはありませんでしたが、この物語が訴えているのはそれとは別の事だと察せます。
遠い将来、何か時代の流れによって再び世界戦争が起きないという保証はありません。
売っている食べ物が沢山あり便利な物が沢山あるという今の環境に、どれだけ恵まれているかを感じることでしょう。

それでは、このドラマ(物語)を想い出しながら簡単に【あらすじ】を観ていきましょう。
2005年平成17年 川崎に家族で暮らしているシステムエンジニアの清水要治は、浅草に来て小学生の頃に仲が良かった宮島敏夫と30数年振りに久しぶりに会った。そして、その2日後のこと。
その朝、妻の紀子に突然変な事を言われて起こされる。
「外が森になっているのよ!」
「お前熱でもあるのか?今薬取ってくるから待ってろよ」
要治は1Fへ降りて薬を探すと、風に揺れる木の影に気づいた。
紀子の言っていたことは本当だった。
自分の家以外の住宅地ごと無くなっていて、ぽつんと1件自宅が森の中だった。

要治は家を出て森の中へ調べに行く。多摩川はあるが景色が全く違った。
進むと人々の声がした。昔の服装で兵隊を送る人たちの姿。
そして木の掲示板に貼ってあった昭和19年の張り紙を不思議に思う。
戻って家族へ観たことを伝えていると、繋がるはずのない電話の鳴る音が。
恐る恐る出ると、2日前に会った宮島敏夫だった。
品川から来るという敏夫を迎えに行くと、息子の新也と一緒だった。
家に迎えて話をすると、息子と釣りに出た時に戻ると時代がおかしくなってたと。
そんな中で突然、兵隊を連れた将校が訪ねて来た。

「妙な家ですね~?道も無いのに見たことのない車も置いてある」
要治は敏夫の様に機転を利かせて「極秘の任務です!」と言い張り追い返した。
しかしバレてしまうのも時間の問題と悟り、できるだけ家の物を土へ埋める。
その後、全員で必要な物を纏めて出ることにし、夜に家を焼き払ったのだった。
ここからなるべく遠くへ逃げなければならないと、トラックを盗んで移動した。

川のほとりで一晩過ごした一行は、元の時代に戻っていることを期待したが、やはり街へ出ると昭和19年のままだった。
要治と敏夫は機転を利かせて、農家の家で1本の折りたたみ傘と米1俵とリヤカーを交換できた。そして一行は立川で空き家になったバーを借りることができ一時を過ごせたが、すぐにあの将校がつきとめてきた。
家の中をくまなく探し回られ、要治が一人の兵士に見つかってしまった。しかし、その兵士はなぜか見なかったことにしてくれたのだ。
その後、太平洋戦争は歴史の教科書の通りに進んでいった。サイパン、グアムを取られ、やがて連合艦隊は消滅していく。そして神風特攻隊も組まれていくのであった。

1944年(昭和19年)秋
要治と敏夫は軍事工場に働いていた。腕時計を売り偽装の謄本を手に入れ、無事に住民登録を取れたのだった。
妻の紀子は竹槍婦人部隊へ通い、娘の信子は郵便配達に務めていた。しかし、息子の稔と敏夫の息子(新也)の二人だけは家に居る状態だった。
夕飯の時、子供たちはデパートやファーストフードを想い出し惜しんでいた。
妻の紀子もこの時代の辛さに要治にあたる。
「お米も少なく、味付けは塩しかないし味噌も砂糖もない、梅干しもやっと手に入れたのよ!」
「石鹸も歯ブラシも無い、油も無ければ酢も無い、シャンプーやリンスなんて影も無い!」
家庭を守る紀子の辛さも分かったが、要治と敏夫も工場で意味の無い辛いパワハラに耐えていたのである。
その夜、敏夫の息子(新也)が独りで家を出て行ってしまったが、敏夫は追いかけはしなかった。
 昭和19年11月24日 夜、歴史通りに初めて東京への空襲があった。
昭和19年11月24日 夜、歴史通りに初めて東京への空襲があった。
子供たちは栄養不足によって体中に痒さが出てしまうので、村へ芋や卵を売ってもらいに行くのだが、お金よりも食料の方が大切な時代なので簡単には売ってもらえないのだ。
村からの帰りに要治も息子の稔も、何でも揃っていた2005年の時代を惜しむのだった。
昭和20年元旦、敏夫が手に入れてきた餅でおしるこを食べることができた。おしるこの味が体に染みた。
そんなある日、要治は考える。
「この先のいろいろな出来事を知っている我々は、ここで何もしなくていいのだろうか?」と。
そこで、これから起こる大きな東京大空襲のことを下町の人々へ知らせて救おうと考えたのだ。
夫婦で食堂へ行って伝えようとしたりビラを作ってポストへ入れたりするが、上手くはいかないのである。
どうしても伝えなければならないと決意した2人は、食堂へ向かい大声で伝えるのだった。しかし、あの将校が居てその場は荒れてしまうのだった。
キズを負って帰ると、敏夫の息子(新也)が無事に戻っていた。見違えるほどになった息子は国のために尽くす青年になっていたのだ。
そんな時、空襲のサイレンが鳴るのである!
歴史を知っている要治は言う。「いや、この辺は大丈夫だ!」
「この辺には被害が出ないはずだから・・」
しかし、広い範囲で焼き尽くされてしまったのである。

要治が目を開け気が付くと、片腕が無かった。
「これでは歴史が違っている・・」
そして、要治の目には辺り一面何もない光景の先に、昭和20年には存在していないはずの建物の跡が見えたのだ。
その時、今にも息絶えそうな男性を見つけた要治は尋ねた。
「今は何年ですか?」
その人は口を僅かに開けて一言「二千‥」
「二千? 二千何年ですか?」
しかし、その人は息絶え、 要治もそれまでだった。
– 完 –

この物語は本当に「深い意味を持っている」と想い出す度に思わされます。
ある日突然、昭和の戦時中に放り込まれた現代人の6人
今はごく普通にある便利な物も食料も、この戦争中の生活にはありませんでした。
その中でも主人公の要治や敏夫は、この全く違う時代に適用し「生きる!」という精神を貫いている、その生きる強さに痛感させられるものでした。
近年、ウイルスパニックや温暖化による天候の猛威が我々を襲ってきていますが、生き残されているうちは諦めずに一生懸命に「生きる使命」を続けるのです。
人には必ずいつか終わりが訪れますが、生きている(生かされている)うちは、そこに意味があるということなのです。